構成文化財 因州高草郡加路浦湊絵図
クリックで拡大
- 説明
-
北前船等の大型船が停泊していたことを示す、鳥取城下の玄関口であった賀露港の江戸時代末期、弘化2(1845)年に描かれた絵図です。賀露港について、水深や地形、船が港に進入するために必要な係留場所などが詳細に描かれています、船の通行条件などが江戸時代の賀露港を知る上で貴重な資料です。
- 関連サイト
-
- かろ広報(日本遺産認定〜北前船関連で賀露神社と構成文化財〜) https://is.gd/NcUr23
- 所在地(Googleマップ) https://goo.gl/maps/WdMwpZno7bYrh2wYA
都道府県
- 鳥取県
市町村
- 鳥取市
類型
- 寄港地
- 船主集落
種別
- 構成文化財
- 絵図
所在地
鳥取県鳥取市賀露町北1-21-8
賀露神社
年代
- 1845年 製作
- 江戸時代
弘化2年
関連情報
非公開
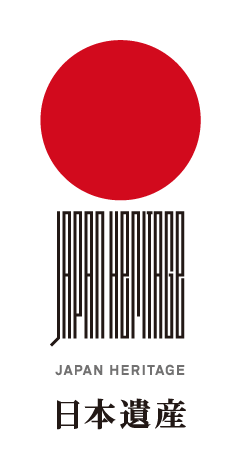
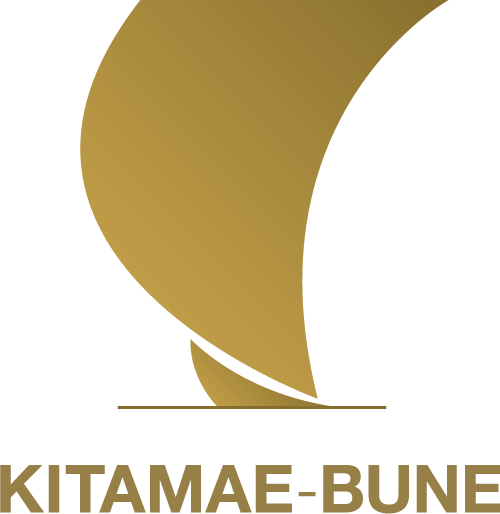




.jpg)
2021.10.20.jpg)



