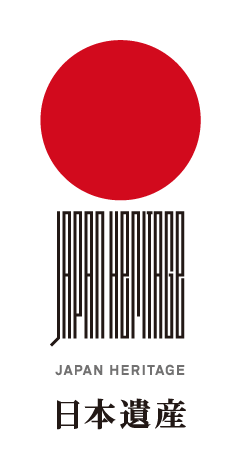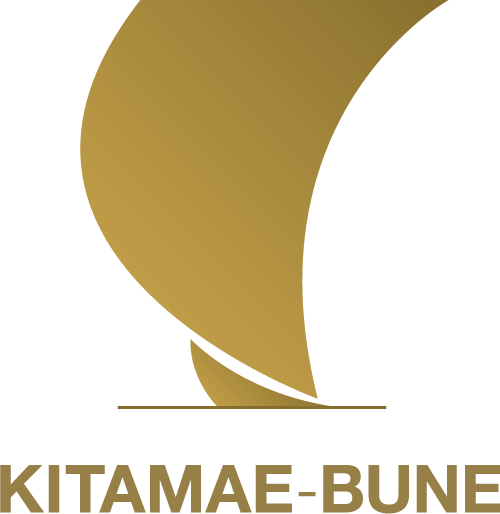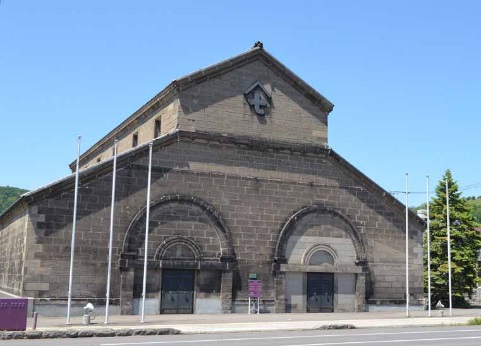構成文化財 住吉神社
クリックで拡大
- 説明
-
北前船の商人たちが信仰した神社。境内地には北前船の船主や問屋らが寄進した玉垣が見られる。
- 関連サイト
-
- 呉市HP(日本遺産「北前船」) https://www.city.kure.lg.jp/site/kitamae/
都道府県
- 広島県
市町村
- 呉市
類型
- 寄港地
種別
- 構成文化財
- 奉納物
- 玉垣
- 石造物(灯籠、玉垣など)
所在地
広島県呉市豊町御手洗字住吉町338-1
指定
広島県重要文化財(1996年)