29件ヒットしました
備前市
瀬戸内海のリアス式海岸の奥に位置する片上は延喜式に登場する古よりの要港です。江戸時代には西国街道の宿場町に指定され、本陣・脇本陣が置かれました。また、伊部で焼かれた備前焼の積出港でもあり、全国各地へと運ばれました。
また、日生諸島の沖合に位置する大多府は天然の良港であり、元禄11年(1698年)に岡山 池田藩によって開かれ、在番所・御用家・加子番所などが置かれました。潮待ち・風待ちの港として、参勤交代の御座船や大型廻船が寄港しました。この中には北前船も含まれていたと推定されます。
概要
瀬戸内海のリアス式海岸の奥に位置する片上は延喜式に登場する古よりの要港です。江戸時代には西国街道の宿場町に指定され、本陣・脇本陣が置かれました。また、伊部で焼かれた備前焼の積出港でもあり、全国各地へと運ばれました。
また、日生諸島の沖合に位置する大多府は天然の良港であり、元禄11年(1698年)に岡山 池田藩によって開かれ、在番所・御用家・加子番所などが置かれました。潮待ち・風待ちの港として、参勤交代の御座船や大型廻船が寄港しました。この中には北前船も含まれていたと推定されます。
都道府県
- 岡山県
市町村
- 備前市
類型
- 寄港地
類型
- 寄港地
構成文化財 大多府漁港元禄防波堤
クリックで拡大
- 説明
-
北前船をはじめ参勤交代の御座船や大型廻船が寄港する岡山藩公儀の港・大多府港の防波堤。
- 関連サイト
-
- 所在地(Googleマップ) https://goo.gl/maps/VCTfibK9WmTUgyMEA
都道府県
- 岡山県
市町村
- 備前市
類型
- 寄港地
種別
- 構成文化財
- 建物
所在地
岡山県備前市日生町大多府244
指定
国登録有形
構成文化財 灯籠堂の石塁
クリックで拡大
- 説明
-
北前船をはじめ参勤交代の御座船や大型廻船が寄港する岡山藩公儀の港・大多府港への道しるべの灯籠堂の石塁。
- 関連サイト
-
- 所在地(Googleマップ) https://goo.gl/maps/hhcWGs3g9FTMfqDJ6
都道府県
- 岡山県
市町村
- 備前市
類型
- 寄港地
種別
- 構成文化財
- 灯籠
- 石造物(灯籠、玉垣など)
所在地
岡山県備前市日生町大多府
指定
市指定(記念物)
構成文化財 大井戸
クリックで拡大
- 説明
-
北前船をはじめ参勤交代の御座船や大型廻船が寄港する岡山藩公儀の港・大多府港にある飲料水提供用の井戸。
- 関連サイト
-
- 所在地(Googleマップ) https://goo.gl/maps/VvMmS58XdGdmxxmY7
都道府県
- 岡山県
市町村
- 備前市
類型
- 寄港地
種別
- 構成文化財
- 石造物(灯籠、玉垣など)
所在地
岡山県備前市日生町大多府115
指定
市指定(記念物)
構成文化財 甚九郎顕彰碑
都道府県
- 岡山県
市町村
- 備前市
類型
- 寄港地
種別
- 構成文化財
- 石造物(灯籠、玉垣など)
所在地
岡山県備前市日生町日生980
指定
市指定(記念物)
構成文化財 北前船の模型 (備前市加子浦歴史文化館)
都道府県
- 岡山県
市町村
- 備前市
類型
- 寄港地
種別
- 構成文化財
- 船模型
所在地
岡山県備前市日生町日生801-4
構成文化財 片上八景 (ゑびすや荒木旅館)
都道府県
- 岡山県
市町村
- 備前市
類型
- 寄港地
種別
- 構成文化財
- 絵図
所在地
岡山県備前市西片上1280
倉敷市
倉敷市には瀬戸内海を望む児島半島の先端に,岡山藩の外港として栄えた下津井,大規模な干拓によって綿花栽培と積み出しで栄えた玉島の両港があります。これらの地域では綿の栽培が盛んに行われ,そのため北前船が運ぶ肥料となるニシン粕が必要でした。玉島は,綿とニシン粕の取引地として,また下津井では帰り荷として綿のほかに児島の塩が喜ばれたそうです。
概要
倉敷市には瀬戸内海を望む児島半島の先端に,岡山藩の外港として栄えた下津井,大規模な干拓によって綿花栽培と積み出しで栄えた玉島の両港があります。これらの地域では綿の栽培が盛んに行われ,そのため北前船が運ぶ肥料となるニシン粕が必要でした。玉島は,綿とニシン粕の取引地として,また下津井では帰り荷として綿のほかに児島の塩が喜ばれたそうです。
都道府県
- 岡山県
市町村
- 倉敷市
類型
- 寄港地
類型
- 寄港地
年代
- 年代不明
関連
文化財
関連
サイト
- 倉敷市HP(日本遺産「北前船寄港地・船主集落」) https://www.city.kurashiki.okayama.jp/33405.htm
- 倉敷市公式観光サイト(かつて北前船が寄港した瀬戸内海を臨む漁港と歴史が息づく町 玉島・下津井てくてくさんぽ) https://www.kurashiki-tabi.jp/extra/kitamaebune/
- 倉敷市日本遺産推進室HP https://www.city.kurashiki.okayama.jp/kura-story/
- 倉敷市日本遺産〜倉敷の歴史を後世に伝える3つのストーリーと倉敷市日本遺産推進室の挑戦(倉敷とことこ) https://kuratoco.com/kurashiki-heritage/
構成文化財 下津井町並み保存地区
クリックで拡大
- 説明
-
下津井は瀬戸内海に面した奈良・平安時代の記録にも出てくる非常に古い港町です。下津井が本格的な港町として栄えたのは江戸時代中期以降からで、北前船による綿花、ニシン粕の取引港として、また讃岐金毘羅参りの宿場としても賑わいました。今でも当時の商家やニシン蔵などが残され、歴史的な景観をとどめています。
- 関連サイト
-
- 倉敷市HP(日本遺産「北前船寄港地・船主集落」) Https://www.city.kurashiki.okayama.jp/33405.htm
- くらしき地域資源ミュージアム(下津井まちなみ保存地区) https://is.gd/0YAeWJ
- 【360度動画|日本遺産のまち 倉敷の旅】 07.北前船寄港地 下津井 篇 https://youtu.be/IlLWfFO0Ekw
- 所在地(Googleマップ) https://goo.gl/maps/V3ebim93UV5YAYt1A
都道府県
- 岡山県
市町村
- 倉敷市
類型
- 寄港地
種別
- 構成文化財
- まちなみ
所在地
岡山県倉敷市下津井
指定
岡山県指定まちなみ保存地区
(1986年)
参考資料
『倉敷市下津井地区歴史的景観調査報告書』(1985年)
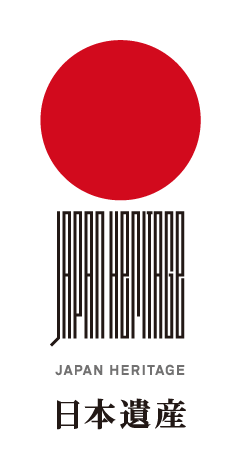
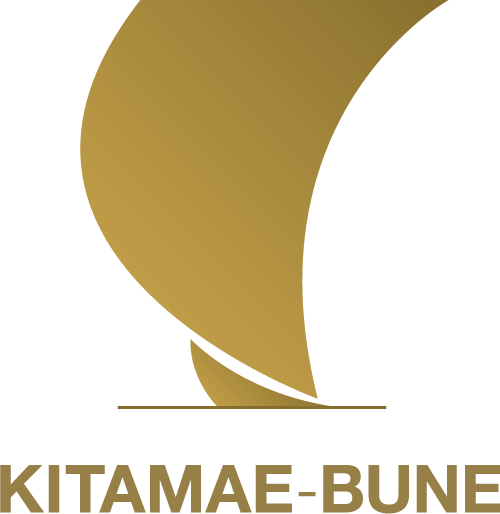





.jpg)


